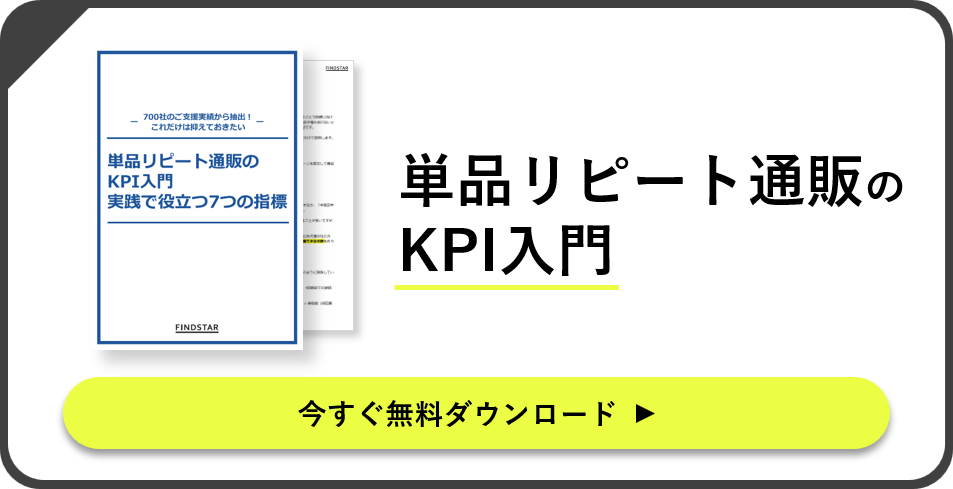特許権の侵害警告などを受けた場合の対応について簡単に説明します。
ものづくり企業のかかえるリスク
明治時代以降、資源の乏しい日本は、当初西欧リードされていた「ものづくり」の分野で驚くべき進歩発展を成し遂げ、経済成長を成し遂げてきました。
主力となった製品は時代ごとに異なりますが、日本人の特性を生かして、高品質・高性能な製品を生み出して世界の市場を席巻したのです。
現在は、サービスや文化の輸出にも重心が移動してきたとはいえ、「ものづくり」が産業の中で重要な役割を果たすことに変わりはありません。
DIRECTAの主要な読者である通販事業を営む皆様の中で、多くの企業が自社製品を販売していることと思います。
お客様に支持される高品質・高性能な製品には、苦労して開発した技術やデザインなどが生かされています。
自分で作り出したものなのだから、自分で製造・販売できるのは原則的には当たり前のことです。
しかし、すべて自社で開発を行ったにもかかわらず、知的財産権の侵害になってしまうことがあるのです。
知的財産権を取り巻く法律には独特の複雑さがあります。
それをできるだけわかりやすくご説明しようと思います。
今回は、自社が製造販売している製品が、特許権を侵害していると指摘された場合について述べます。
特許権の侵害とは何か
特許権の侵害とは、登録されている特許の「請求の範囲」に記載された発明について、他人が特許権者に無断で事業を行うことをいいます。
特許権を取得するためには、特許庁への出願手続きを取ることが必要ですが、他人がこの出願手続きをした後で、自分が同じものを独自に発明した場合はどうなるでしょうか。
同じ知的財産権の分野に属する著作権と比較してみましょう。
著作権の場合、侵害が成立するためには侵害者の著作物が元の著作物に依拠していること、つまり元の著作物を知っていて模倣したということが必要となります。
著作権は、「財産権」ではありますが、その立法趣旨の根本には「人格権」があります。
著作権法の第1条にはその法目的が、
「この法律は、著作物(中略)に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
と定められています。
目的は「文化の発展への寄与」なのです。
したがって、人の心が独自に創り出したものであれば、内容が重複してしまっていても、それを禁じる必要はありません。
ただ、「模倣」は原則として創作ではないので、そのような行為があれば原著作者の権利を守る必要があります。
それに対し、特許法第1条では法目的を
「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」
と規定しています。
一般に、特許制度は発明者の経済的保護を目的としているように捉えられています。
しかし、特許法の本当の目的は「発明の利用」です。
特許出願という形で発明を公開することによって、他人が重複研究・重複投資を行う無駄を回避し、その先の技術の改良・発展を促進することができます。
しかし、人材・時間・費用をかけて開発した技術をただで公開したのでは、先行投資を回収する前に他人に模倣されてしまうので、発明者は保護がなければ、新技術を隠そうとするのが自然です。
そのため、一定期間新しい発明を保護する制度を敷いて、新技術の公開を促しているのです。
ですから、特許制度においては、先に出願という行為を行った者が、先に社会に貢献する行為を行ったということで、優位に立つことができるのです。
しかも、同じ新技術を二重に保護しても産業の発達に寄与することにはならないので、最初に出願して特許権を得た者だけが保護されます。
しかし、特許権法では、真似していようがいまいが、特許発明と同じ発明を実施してしまえば侵害となります。
同じ分野の研究を行っていて、偶然同じものを発明してしまった場合、たとえ自分で苦労して発明したものであっても、その発明について特許権を得ることも実施することもできません。
警告されたらおわりなのか
著作権侵害訴訟では、まず侵害されたという作品が「著作物」に該当するかどうかが争われる場合がしばしばあります。
著作権が発生するためには「登録」という行為は必要ではありません。
そこで、その作品が「創作されたもの」なのか、単なる事実であって何ら「創作性を有しないもの」なのか、ということがはっきりしないと、その後の「侵害」が成立するかどうかの議論に進むことができません。
そこで、「著作物」と認められた判決が確定すれば、その後その作品が「著作物でなくなる」ということはないのです。
しかし特許の場合、話は違います。
特許が無効になり、特許権が存続期間の満了前に消滅することがあるのです。
特許が有効である、あるいは無効である、ということある理由は、特許権の成立過程が関わっているのです。
特許を受けるためには、以下のような手順によります。
まず、発明を特許出願の願書に添付する書類に記載します。
そして特許庁に出願した後審査請求を行うと、審査官が特許すべきかどうか審査します。
この「特許すべきかどうか」の内容は少々ややこしいのですが、非常に単純化して言うと、以下の場合には特許を受けることができません。
① 自分の出願に係る発明が、出願されるより前に第三者に知られていた
② 自分の出願に係る発明が、出願前に第三者に知られている発明に基づいて容易に発明することができた
③ 自分の出願に係る発明が、自分が出願する前に第三者によって出願されていた。
このような条件に該当しなければ、審査官は特許査定を下します。
しかし、特許された後で、上記の3要件に該当することがわかった場合には、特許は無効となります。
無効審決が確定すると、特許権は初めから存在しなかったものとみなされます。
では何故上記の要件をクリアしたはずの特許が、後から無効にされることがあるのでしょうか。
審査官は、出願に係る発明が属する技術分野を中心に、その周辺技術も含めて調査します。
しかし、特許庁への出願件数は膨大で、一人の審査官が抱える審査件数は欧米に比べてかなり多く、周辺技術を調べるといっても、何もかも調査するわけにはいきません。
また、保護される発明を記載する欄を「特許請求の範囲」といいますが、ここには日本語で記載しなければなりません。
出願書類には機械の構造の図面なども添付されますが、それはあくまでその日本語文章記載の理解を助けるためのもので、権利範囲はあくまで、日本語で書かれた技術文献である「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められます。
この記載された発明が、過去に第三者に知られた発明などと同一であるのか(新規性があるか)、過去に第三者に知られた発明に基づいて容易に発明することができるのか(進歩性があるか)、を判断するのは簡単なことではありません。
もちろん審査官は当該技術分野の専門家ではありますが、特に進歩性の判断は難しいものがあります。
そこで、事後的に権利の有効性を判断する審判制度が設けられています。
特許権の侵害警告を受けたり、侵害訴訟を受けたりした側は、審査官の見落としはなかったか、審査官の調査していない周辺技術の中に、同一や類似の発明はないか、あるいは、いくつかの発明を組み合わせることによって容易にその発明をすることができないか、などを徹底的に調査し、見つけたら無効審判を請求します。
その結果として、出願時に実際は特許要件を備えていないことが判明して、特許が無効になることがあるのです。
特許権をめぐる攻撃と防御
特許権者が自己の特許権を侵害されたとして、製造販売をやめるように、などの内容の警告をした場合、警告を受けた者はどのように対応するのでしょうか。
一般的な例を、簡略に図示してみました。

自己の製造販売する製品が特許権を侵害していると警告された場合、ます、侵害の成否を検討します。
具体的には、自己の製品に係る技術が、警告者の特許発明の技術的範囲に属するか否かを検討します。
検討の結果、技術的範囲に属していることがわかったら、当該特許について無効理由を検討します。
無効理由があれば無効審判により特許権を遡及消滅させることによって侵害が成立しなくなるからです。
無効理由を発見できなかった場合は、製造販売を中止するか、設計変更をして、特許権の侵害にならないようにします。
製造販売を継続したいなら、和解やライセンス許諾の交渉をします。
一方、特許権者側は、無効審判で特許無効と判断されその審決が確定すると、特許権が消滅し、したがって権利行使もできなくなってしまうのです。
無効審判で請求が棄却されれば、特許はそのまま有効であり、特許権を行使することができます。
売られたケンカは買わなきゃならない
特許権の侵害警告を受けただけならば、無効審決を勝ち取ることができれば問題は解決します。
しかし、侵害訴訟が提起されてしまったあとでは、それだけではいけません。
侵害訴訟は民事訴訟ですから、民事訴訟のルールに則って審理されます。
原告の訴えに対し、被告は、この事実については争わない、この事実については争う、という選別を行います。
そして、争うと決まった事実について、原告被告双方が証拠を提出し、それを裁判官が判断します。
審理上争いのない事実であるとされてしまったことは、原則として客観的にどんなに間違っていても、民事裁判上は相手の言い分を認めたことになります。
売られたケンカは買わなきゃ負け、というのが、民事訴訟のルールなのです。
したがって、侵害訴訟と並行して無効審判で争っている場合、侵害訴訟でも特許が無効になることを主張しておかないと、せっかく無効審決を勝ち取っても裁判の証拠として採用されない場合があるので注意が必要です。
なお、特許の有効性が争われるのは、特許庁への無効審判だけではありません。
侵害訴訟で、請求の根拠となる特許が無効であることを主張してその主張が通り、有名無実の権利に基づく権利行使は認められない、との判決が下されることがあります。
ただし、それはあくまでその裁判の当事者同士の問題で、そういう判決が出たからといって、特許庁が自動的に特許を抹消したりすることはありません。
特許権をどうしても消滅させたければ、裁判で提出した証拠を基に、特許庁に無効審判を請求しなければならないのです。
* 知的財産権や訴訟についてお馴染みでない向きには、ちょっと分かりにくいお話だったかもしれません。
この件について、また、他の知的財産権などについてご質問、ご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。