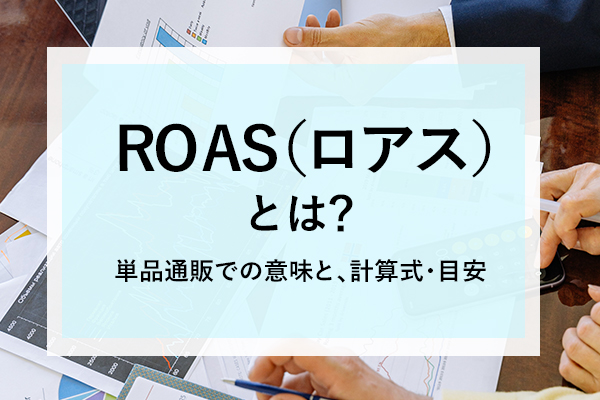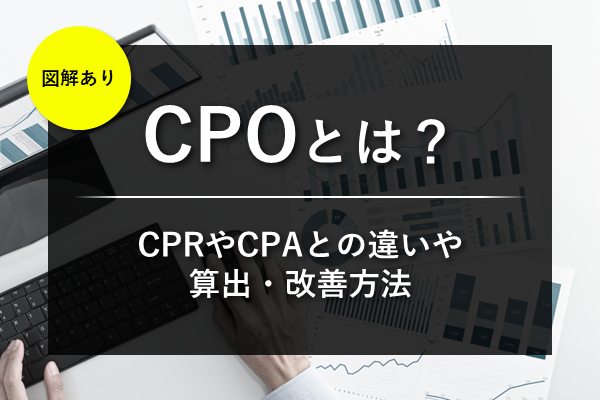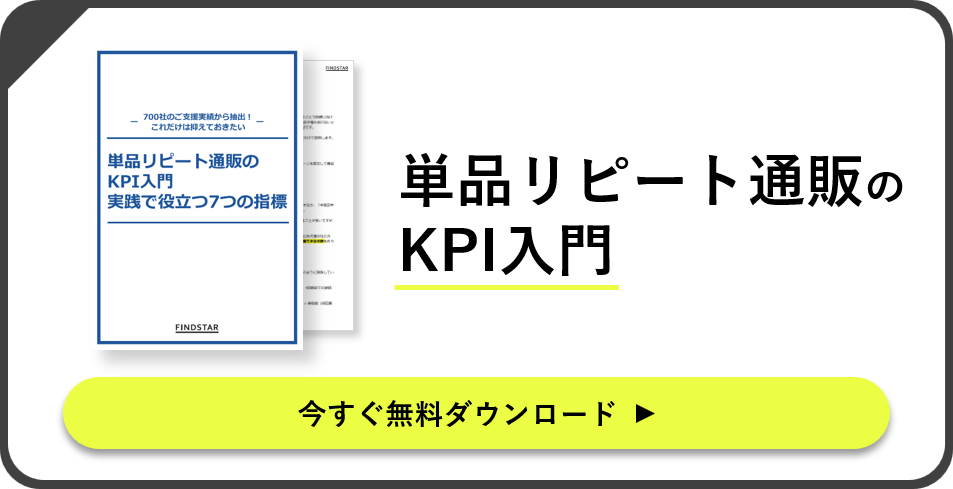広告費の割合は、同業種の平均や事業計画、CPO・CPAを基準に決定することが多いです。本記事では、上場企業における広告費割合の平均や業種別・媒体別の広告費割合を解説します。また、通販ビジネスの視点から、広告費の費用対効果を高めるポイントも紹介します。
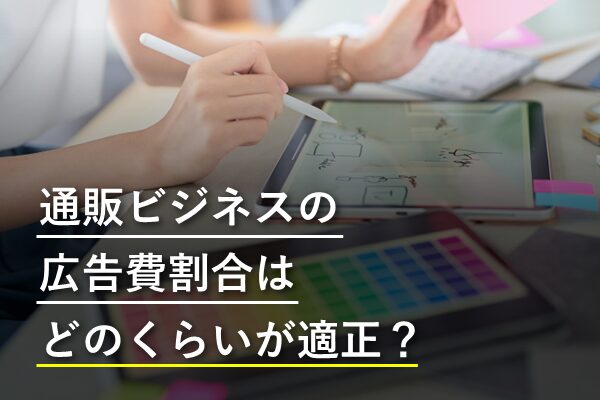
通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。
KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。
⇒解説資料はこちら
目次
広告費の割合【業界・業種別】
はじめに、上場企業における広告費割合の平均や、業界・業種別における広告費の割合を紹介します。
上場企業における広告費割合の平均
上場企業のうち4分の1(約920社)を対象にした調査では、広告宣伝費が売上高に占める比率は平均で3.5%という結果が出ています。
通販・ECにおける割合
通販やECといった業態では、「店舗を持たない」という特性もあって、新規顧客を獲得するために多額の広告宣伝費を使います。日本通信販売協会(JADMA)の調査によると、2015年度の通販売上高に占める広告宣伝費の平均割合は、20.1%。
(「第34回通信販売企業実態 調査報告書」より)
特に化粧品や健康食品など「単品リピート通販」と呼ばれるビジネスモデルでは、費用の5割近くを広告宣伝費が占めることも珍しくありません。大企業が新規参入する場合や、ベンチャーキャピタルなど資本が入っている場合は、事業の成長を加速するために、初期には売上を上回る広告宣伝費を一気に投入することもあるくらいです。
【業種別】売上高広告費比率の平均
経済産業省企業活動基本調査によると、全業種平均および主な業種における売上高広告費比率は以下のとおりです。なお、下記データは中小企業のデータも含まれているため、上場企業の平均と比較すると低い数値であると考えられます。
- 全業種平均:0.667291593%
- 無店舗小売業(通販、ECなどを含む):5.709571962%
- その他の洗濯・理容・美容業・浴場業:9.465869361%
- 飲食サービス業:1.118743164%
- 医薬品・化粧品小売業:1.663068811%
- 食料品製造業:1.093542462%
- クレジットカード業、割賦金融業6.218776916%
前述した通販・EC単体のデータおよび上記のデータから、通販ビジネスにおける広告宣伝費の割合は高いと言えるでしょう。
広告宣伝費の割合が高い上場企業ランキング
広告宣伝費の「売上比率が高い200社」ランキング(東洋経済オンライン)によると、広告宣伝費の割合が多い上場企業の上位10社は以下のとおりです。
| 順位 | 企業名 | 売上高広告費比率 |
|---|---|---|
| 1 | 東京通信 | 53.41% |
| 2 | ファーマフーズ | 53.17% |
| 3 | リビン・テクノロジーズ | 52.37% |
| 4 | 出前館 | 51.31% |
| 5 | アトラエ | 47.96% |
| 6 | ポート | 44.26% |
| 7 | ジェイフロンティア | 41.40% |
| 8 | キャリアインデックス | 41.34% |
| 9 | エイチーム | 39.61% |
| 10 | KIYOラーニング | 39.22% |
見てのとおり、上位の企業は平均を大幅に上回る割合で広告宣伝に予算を割いていることがわかります。
通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。
KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。
⇒解説資料はこちら
媒体別の広告費
電通の資料によると、2022年における「マスコミ4媒体広告費」、「インターネット広告費」、「プロモーションメディア広告費(DMや折込など)」それぞれの割合は以下のとおりです(カッコ内は前年比)。
- マスコミ4媒体広告費:33.8%(-2.3%)
- インターネット広告費:43.5%(3.7%)
- プロモーションメディア広告費:22.7%(-1.4%)
マスコミ4媒体とプロモーションメディア広告の構成比は減少した一方で、インターネット広告費の割合は前年比で増加しています。
各媒体のより詳細な広告費の割合もお伝えします。
マスコミ4媒体
4媒体それぞれが全体の広告費に占める割合は以下のとおりです。特に、テレビメディア(地上波テレビなど)での減少が顕著です。
インターネット
全体の広告費に占める各広告の割合は以下のとおりです。4媒体由来のデジタル広告で増加が顕著となっており、特に媒体費の中でも「テレビメディア関連動画広告費」の増加が大きいとのことです。ただし、伸び率は大きいものの、インターネット広告の媒体費に比べて金額自体は大きくありません。
| 媒体名 | 構成比(カッコ内は前年比) |
|---|---|
| 媒体費 | 34.9%(+3.2%) |
| 物販系ECプラットフォーム広告費 | 2.7%(+0.3%) |
| 制作費 | 5.9%(+0.2%) |
プロモーションメディア
全体の広告費に占める各広告の割合は以下のとおりです。全体的に微減となっています。
| 媒体名 | 構成比(カッコ内は前年比) |
|---|---|
| 屋外 | 4.0%(±0%) |
| 交通 | 1.9%(-0.1%) |
| 折込 | 3.7%(-0.2%) |
| ダイレクトメール(DM) | 4.8%(-0.3%) |
| フリーペーパー | 2.0%(-0.1%) |
| POP | 2.1%(-0.2%) |
| その他(イベント、展示など) | 4.2%(-0.5%) |
出典:2022年 日本の広告費(電通)
通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。
KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。
⇒解説資料はこちら
広告宣伝費とは?基本をおさらい
広告宣伝費の最適な割合を検討するには、まずは費用の意味や種類を理解しておくことが重要です。この章では、広告宣伝費の基本的な部分をおさらいしておきましょう。
広告宣伝費の意味
経済産業省の調査資料では、広告宣伝費を「商品・サービス・会社などを広く一般に知らせるために行う、新聞・テレビなどの広告媒体への広告や宣伝にかかる費用の額」と定義しています。簡単にいうと、商品やサービス等の認知度や魅力を多くの人に知ってもらうためにかかる費用です。
素晴らしい商品・サービスを作っていても、それをターゲットとする見込み客に認知されていなければ収益は得られません。また、単純に認知されているだけで魅力が伝わっていないと、購入やお問い合わせなどのアクションにつながりません。
商品を知ってもらい、かつ購入につなげることで「売上を最大化」する上で、広告宣伝費は欠かせないと言えます。
広告宣伝費の種類
一般的に、以下の費用が広告宣伝費となります。
- テレビや新聞、Web等の媒体に出稿した広告代
- カタログやダイレクトメール、販促用チラシなどの作成費用
- 広告宣伝を目的としたノベルティ作成の費用
- 見本品やサンプル等の作成費用
一方で、取引先に送る贈答品やイベントへの協賛金などは、広告宣伝を目的としていないため広告宣伝費に該当しません。
「広告宣伝を目的としているか(実際に広告宣伝の効果があるかどうか)」を基準に、広告宣伝費に当てはまるかどうかを検討すると良いでしょう。厳密に税務や会計上、広告宣伝費に当てはまるかどうかを検討したい場合には、税理士などの専門家に判断を仰ぐことがおすすめです。
出典:広告宣伝費 | 調査項目情報(政府統計の総合窓口)
通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。
KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。
⇒解説資料はこちら
通販とその他業種における広告費に対する考え方の違い
なぜ通販ビジネスでは、このように多額の広告宣伝費を投資するのでしょうか?
それは、広告宣伝費への考え方が一般のビジネスとは異なるからです。
一般的なビジネスでは、「間接費」の扱い
先ほど例に出た、化粧品を販売するメーカーを考えてみましょう。
ドラッグストアや百貨店など小売店がメインのチャネルの場合、広告の果たす役割は限られています。商品を売る見込み客は、店舗に集まってきた人たち。その方たちの目に届くように、「どうやって良い棚を確保するか?」や「接客して購入まで至らせるか?」が売上を上げるキーです。
企業からの受注がメインの、BtoBビジネスも同様です。
法人営業の主戦場は、対面での商談。近年ではBtoB企業でも広告を出稿する企業も増えましたが、新規でクライアントを獲得するためには、電話営業や人脈・紹介に頼るのがまだまだ一般的です。広告を直接受注につなげられている企業はまだ一部の企業のみです。
これらのビジネスにおいて広告宣伝は、「側面から援護する」という意味では効果的ですが、販売や営業とは切り離されていることが多いもの。したがってその費用は、あくまで間接費という扱いです。
通販ビジネスでは、「直接費」の考え方
しかし通販ビジネスには、顧客が訪れる「店舗」がありません。また、足を使って顧客を開拓する「営業マン」も置いていません。
通販ビジネスにおける広告は、「売り場」にたとえられることが多いです。チラシやLPなどを見た方がその場で商品を購入してくれるように設計します。商品を買ってくれる顧客を集めるためには、「広告」が大きな役割を果たします。
したがって、通販での広告宣伝費は、「人件費」や「店舗費用」に相当するものととらえられます。ビジネスを側面から支援する間接費用というよりは、販売の根幹をつくる直接費用としての色合いが濃いのです。
広告宣伝費によって手に入れるのは、新規顧客のリスト。顧客さえ集まれば、メールやDM、電話とあらゆる連絡手段によって、商品を販売できます。比喩的な言い方ですが、通販ビジネスでは、顧客を「仕入れる」ために広告宣伝費を使うのです。
通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。
KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。
⇒解説資料はこちら
広告宣伝費の効果測定に用いる3つのKPI
これまで見てきたとおり、広告宣伝費にしっかり投資するのが望ましいといっても、ムダ使いしてしまっては意味がありません。
広告宣伝費を効率的に活用できるように、KPIを設定して管理していく必要があります。さまざまなKPIのなかでも特に重要な指標が、CPO、ROAS、LTVの3つです。
広告投資の効率をはかるのが、CPO
CPO(Cost Per Order)とは、新規顧客に本商品や定期コースを購入してもらうために、1件あたりにかかった広告費用を指します。「新規顧客の獲得単価」とも、言い換えられるでしょう。
たとえば、100万円の広告費を投入して、200件の新規購入があった場合で計算しましょう。
100万円(広告宣伝費)÷200件(受注件数)=5,000円(CPO)
この5,000円が、CPOです。
通販のビジネスモデルでは、このCPOが低くなればなるほど、利益が大きくなります。利益が大きくなると広告投資にも予算をさらに割くことができ、広告投資が増えると獲得できる新規顧客が増えてさらに利益が増える、という好循環が生まれます。
売上に対する広告の貢献度を表すROAS
ROAS(Return on Advertising Spend)とは、広告から獲得した顧客の売上によって、広告費をどの程度回収できているかを表す指標です。たとえば、200万円の広告費をかけて、400万円の売上を獲得できた場合で計算してみましょう。
400万円 ÷ 200万円 = 200%(ROAS)
上記より、1回の売上で広告費の2倍におよぶ金額を回収できたと言えます。
ちなみに、単品リピート通販のビジネスモデルでは、1年間の累積売上でROASを計算します。理由としては、初回の売上は広告費を下回るケースが大半であり、リピートを前提としているためです。
ROASが高いほど、売上に対する広告費の貢献度が高いと判断できます。広告の費用対効果を高め、よりスピーディーに投資資金を回収するためには、ROASを高める施策が求められます。
LTVで「中長期的な広告の効果」を測定
LTVとは、“Lifetime Value”の略、日本語では「生涯顧客価値」と訳されています。お客様一人ひとりが生涯にわたって、どれだけ自社の商品・サービスを買ってくださるか?そのトータルの売上を合計した金額が、LTVです。
顧客の回転の早い通販ビジネスでは、初回購入から1年間の売上の合計として出すのが一般的です。
たとえばAさんというお客様が、2016年4月に2,000円のトライアルセットを注文、5月から12月まで8ヶ月間、4000円の化粧水を毎月購入くださいました。
さらに、9月には7,000円の美容液も買ってくださっていましたが、2017年1月からは商品の購入をやめてしまいました。
この場合のAさんのLTVは、2,000円+4,000円×8+7,000円=41,000円です。
通販ビジネスは、商品を一度買ってくださった方と末永くお付き合いして、くり返し購入してもらうことによって、売上を高めていくビジネスモデルです。いくらCPOが低く効率的に獲得できたとしても、その広告で獲得したお客様にリピートしてもらえてなければ、その広告は収益に貢献したことになりません。
したがって、獲得したお客様一人ひとりがどれだけお金を使ってくださるか?、すなわちLTVを高めていくのが重要です。
通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。
KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。
⇒解説資料はこちら
広告費における割合の決め方
これまで、通販ビジネスにおける広告宣伝費の考え方と、その効率性をはかるKPIをテーマに解説してきました。この章では、広告費の割合を決める方法を紹介します。
一律の基準はなく、企業ごとに判断するのが基本
説明してきた内容からもお分かりと思いますが、通販ビジネスにおいて「広告費は売上の○割が適正」「○%〜○%の範囲におさめるべき」といった一律の基準はありません。広告宣伝費の役割を理解したうえで、企業ごとに数字を見ながら収益を最大化するために判断していくことが基本です。
そのための投資判断の基準は、「単品通販の収益構造を「数字」で分析・改善するための、必読記事3選」が参考になりますので、よろしければご覧ください。
広告費の割合を検討する基準
企業ごとに判断するのが基本とはいえ、「どのように判断すべきなのか」は気になる部分かと思います。
そこで、この項では広告費の割合を検討する基準を3つ紹介します。
①同業種平均を基に、売上高に応じて一定割合とする
1つ目の基準は、同業種における広告費割合の平均を、自社の売上高に対する広告費の割合とする方法です。
たとえば、通販業界における広告費の割合平均が20%、自社の売上高が1億円だとします。
この場合、自社の広告費割合は、平均と同様に20%とします。
したがって、広告費の予算は1億円×20%=2,000万円となります。
比較的簡単に広告費の割合や予算を決定できる点がメリットです。また、同業他社の平均をベースとしているため、ある程度は合理的な割合となります。ただし、自社の実態や計画・戦略に適さない場合もあります。
②今後の事業計画に基づいて決定する
2つ目の基準は、今後の事業計画です。今後の事業における方針に基づいて、広告費の割合を多めに取るか少なくするかを検討します。
売上やユーザー数を最大化したい場合には、広告費の割合を多めに確保することが適しています。理由としては、広告からある程度の売上が確保できている場合、理論上は広告費をかければかけるほど、売上を上げることができるためです。特にユーザー数が大事なアプリ系の企業は、広告費に多くの予算を割いている傾向が大きい印象です。実際に、広告宣伝費の割合が高い上場企業ランキングTOP10の企業の中でも、東京通信、出前館、アトラエ、エイチームはアプリ事業を持っています。
一方で利益を最大化したい場合には、広告費の割合を現状維持または減少させることが一般的です。広告費の割合を減らすことで、売上が維持できれば利益率を高めることができるためです。通販業界では、広告費の割合を一旦かなり減らし、引き上げ率アップや定期継続率アップの施策を行う企業も少なくありません。
③CPOやCPAから逆算する
広告費の割合を検討する際には、「効率的に売上を獲得できるかどうか」を重視する考え方もあります。その際に有用となるのが前述した「CPO」や「CPA」という指標です。
CPO(Cost Per Order)は前述のとおり、新規顧客に本商品や定期コースを購入してもらうために、1件あたりにかかった広告費用です。
一方でCPA(Cost Per Acquisition)は、コンバージョン(本商品購入やサンプル申し込みなど)の1件あたりにかかった広告費を意味します。「広告費 ÷ コンバージョン数」の計算式で算出されます。広告費が100万円、コンバージョン数が100件の場合、CPAは100万円÷100個=10,000円となります。
なお、EC通販をはじめとした2ステップマーケティングのビジネスモデルでは、「Web広告→お試し・サンプル申し込み」における獲得単価をCPA、「お試し・サンプル→本商品購入・定期申し込み」の獲得単価をCPOと区別することが一般的です。
CPOやCPAが適正値(多すぎない・少なすぎない)となる水準に広告費の割合を設定することで、最低限のコストで最大の売上を得られるようになります。CPOやCPAの適正値は、商品単価やビジネスモデル(売り切り型かリピート型かどうか)によって変わってきます。
CPOやCPAについては、以下の記事でくわしく解説しています。
通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。
KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。
⇒解説資料はこちら
広告宣伝費の費用対効果を高めるポイント
広告宣伝費の費用対効果を高めるには、最適な割合を考えることに加えて、以下3つのポイントを押さえることが重要です。
- ターゲット顧客のペルソナを明確化する
- 費用に対する効果が高い媒体を優先的に活用する
- PDCAを回し続ける
以下では、各ポイントをくわしく解説します。
ターゲット顧客のペルソナを明確化する
基本的なポイントとして、ターゲット顧客の人物像(≒ペルソナ)を正確に捉えることが大切です。
ターゲット顧客のペルソナがぼやけていると、商品・サービスの訴求も明確でなくなり、「誰にも刺さらない」広告となってしまいます。誤ったペルソナ設定をしてしまうと、本来ターゲットとしている顧客のニーズには刺さらない広告となってしまい、期待している効果を得られなくなります。
こうした事態を避けるためにも、まずはターゲット顧客のニーズや趣味趣向、年齢、性別などを詳細に分析し、ペルソナを明確化することが大切です。定めたペルソナをもとに、適切な媒体選びを行い、ニーズに応じた広告のクリエイティブ制作を行うことで、広告の費用対効果を高められるでしょう。
当たり前なことですが、まずは基本を押さえることが重要です。
費用対効果が高い媒体を優先的に活用する
一般的に、広告宣伝は1つの媒体に絞るのではなく、WebやDM、テレビCMなど複数の媒体を活用するケースが多いです。しかし、適切な媒体選定を行わずに広告を出稿すると、効果の薄い媒体にも広告費を使うことになり、利益率を悪化させる要因になります。
少ないコストで売上につなげるには、費用対効果の高い媒体に対して多めに広告費を割くことが大切です。たとえば、若者であればYouTubeやWeb広告が効果的である場合が多いですし、シニア層の場合は新聞やラジオなどの広告が効果的です。
とはいえ、基本的にほとんどの企業は、Web広告から始めた方が良いと考えられます。その理由は以下の2点です。
- 最低実施金額の設定がないため、オフライン広告に比べて自社に合わせた金額で開始できる
- すべてWeb上で設定するので、PDCAが回しやすい
ただし、唯一ターゲットが60代以上のシニア層の場合にはWeb広告はおすすめできません。理由としては、ターゲットとなるシニア層がWeb上にあまりいない可能性が高いためです。60代以上を狙う場合は新聞、テレビ、ラジオなどのオフラインの媒体を検討するのが得策です。
また、現時点で出稿している各広告の費用と効果を分析し、コストパフォーマンスが悪い媒体は別のものに変更する・出稿をストップするなどの対応を行うのも、よいでしょう。
PDCAを回し続ける
広告を実施した場合、やったきりにならずに効果の測定をし、良い/悪いの判断を行った上で、次の広告出稿に向けて改善を行っていくことを忘れないようにしましょう。
たとえば前述した指標(CPOやROASなど)に加えて、CTRやCVR、入札額などの指標を多角的に分析し、現時点における広告出稿の効果を分析します。一部の指標に問題点が見つかった場合には、その原因を突き止め、改善を図ります。このサイクルを続けることで、広告の費用対効果を高めることができます。
注意すべきなのは、現時点で効果の高い施策でも、消費者ニーズや市場環境の変化によって効果が低くなる可能性があることです。現時点で優良な施策でも定期的に効果を測定し、市場の変化等によって効果が悪化した場合には、いち早く対策を講じることが重要です。
通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。
KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。
⇒解説資料はこちら
状況や戦略に応じて広告費の割合を検討しよう
広告費の割合に決まったルールはなく、最適な配分は状況や経営戦略に基づいて決定することが重要です。近年はマスメディアと比べて、インターネット広告費の割合が増加しており、どのメディアにどれくらいの広告費を割くか?は時代とともに変化していくといえます。
また、広告宣伝費の良いところは、資産計上をする必要がないことです。広告宣伝費を活用して獲得するのは、顧客リストという「資産」。しかし、会計上はその投資を「費用」として計上できます。したがって、事業が黒字で効率良く顧客を獲得できているときには、広告宣伝費をどんどん投入して未来の収益を手に入れるのが得策となります。
通販事業の発展のために、広告宣伝費へ積極的に投資して効率的に活用する。この記事が、その一助になれば嬉しく思っています。
通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。
KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。
⇒解説資料はこちら