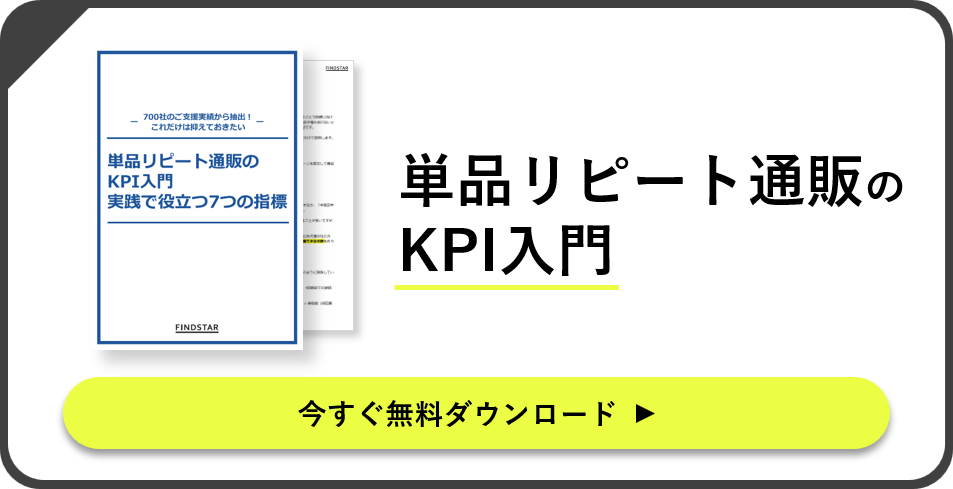前回は、特許権の侵害警告などを受けた場合の対応について簡単に説明しました。
前回記事:『通販のための特許権の侵害と侵害警告への対策 第一回』
今回は、誤って特許権を侵害してしまうことを裂けるために、どのようなトラブル防止策を講じたらよいのかを説明してみましょう。
1.危機管理上の大原則
前回までに述べたように、知的財産という無体財産権であっても、民事訴訟の対象となれば「もの」として扱われ、原則として損害賠償を請求したり土地の所有権を争ったりする裁判などと同じ手続で進められることになります。
通常、訴訟となれば企業の法務部門が対応するでしょうが、訴訟の対象が知的財産権である場合、それを管理する知財部門との連携が問題となります。
知財部門は、特許等の出願の担当部署として、開発部門と密接な関係を持っています。
したがって、メンバーも技術系の人間が中心となる場合が多いと思いますが、知的財産権がしばしば訴訟の対象となる以上、訴訟対応上の齟齬を来たさないように、法務部門と知財部門が一つの問題を有機的に、包括的に取り扱うようにしておかなければなりません。
侵害訴訟対応において、知財部門は主に、訴訟の根拠となる特許発明と、実施された製品に使用された発明の内容が抵触しているかどうかの判断や、その特許権が無効理由を有しているかどうかの判断を担当することになるとは思います。
知財部門は技術を担当する開発部門と、法律を担当する法務部門との架け橋になる立場ですから、技術に対する理解が必要なのはもちろんですが、法務部門との連携も大事なので、民法や民事訴訟法について一定レベルの知識がある人間も配置しておく方がよいと思います。
民事訴訟法第157条には、
「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」
という規定があります。
せっかく特許無効の証拠をそろえていても、侵害訴訟の中の適切なタイミングで証拠を摘出していなければ、証拠として採用されず、無効であるはずの特許が有効であるとして、敗訴することもあるのです。
そして、危機管理上の大原則は、事件を一元管理することです。
訴訟は危機管理上の大問題ですから、危機管理部門は、法務、知財、技術の3部門からの情報を総合して、適切な判断ができるようにしておかなければなりません。
2.技術調査の観点から
訴訟の被告になると、大変な手間とお金がかかりますが、実はこれは原告側も同じです。
したがって危機管理上一番大事なのは、訴訟にならないようにすることです。
大石内蔵助は、「松の廊下」事件以降は名家老だったかもしれませんが、本当の危機管理とは、「松の廊下」を起こさないことなのです。
そのためには、自社の技術分野における技術情報をどれだけ把握しておくかどうか、が極めて重要となります。
(1) 自社技術の把握
まず、自社で製造販売する製品等が、どのような技術によるものであるか、きちんと把握していなければなりません。
そのためには、研究開発部門と知財部門の連携を常に緊密にしておかなければなりません。
具体的には、ベース処方の権利フリーの確認だけでなく、改良を行った段階で研究開発部門から知財部門へ再調査要請するルーティンを定めるなど、連絡を密にするべきです。
(2) 他社技術の把握
① 特許公報の閲覧
特許出願は、出願から1年6ヵ月経過すると、公開公報が発行され、誰でも閲覧できるようになります。
これは、出願人、出願日、その発明が属する技術分野、キーワードなどによって検索することができます。
詳しくは、特許電子図書館のホームページをご覧ください。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
② ニュースリリース
特許出願から公開までは1年6ヵ月かかるので、他社が出願直後から製造販売を始めた場合、公報の閲覧からでは他社の技術を把握できない場合もあります。
まず、新製品発売の発表があれば、その製品がその会社のこれまでの開発傾向からどのようなものであるかを類推することも重要です。
この際にはパテントマップ(後述)が有効なツールとなります。
③ 製品分析
やはりまだ公報が発行されていない場合や、独占権の取得よりもノウハウの秘匿を重視して特許出願されていない場合には、発売された他社製品を購入し、使用されている技術を分析することが重要です。
機械やソフトウエアの場合、リバースエンジニアリングにより、構造やソースコードを解明することはよく行われています。
医薬品や食品であっても、開発に携わる研究部門は成分分析により、少なくとも他社製品が自社が現在開発中の製品の成分を既に使用しているか否かは、解析可能なはずです。
研究機関を自前で持たない販売会社であっても、OEM先の事業所では分析技術を持っている場合が多いです。
また、分析のみを外注することもできます。
医薬品や食品は、成分自体は製品に表示してありますので、問題は配合比率になる場合が多いです。
未知の物質を探すような困難な分析はめったにないと思います。
④ パテントマップ
パテントマップとは、ⅰ)特許情報をⅱ)調査・整理・分析しⅲ)視覚化・ビジュアル化したものです。
ⅰ) 特許情報は、技術情報としての側面と、権利情報として側面の2つの側面があります。
ⅱ) 調査・整理・分析については、パテントマップの作成目的に応じて、調査のやり方、調査結果の整理の仕方が異なります。
競合他社の出願件数が知りたいのか、どの技術分野についてなのか、その中のさらに細部を見るのか、時系列で見るのか、発明者で見るのか、などの様々な観点から整理する必要があります。
ⅲ) 視覚化・ビジュアル化については、パテントマップを誰に何のために見せるのかにより、それに適した方法で表現する必要があります。
また、目的に応じて図面・グラフ・表などの形式を考える必要があります。
<例:電子ゲームの 内容、入出力手段別 出願件数マトリクス>

現在公開されている特許公報にはまだ掲載されていなくても、パテントマップによって競合他社がその分野に手厚く研究しているかどうかを知ることができれば、対策を立てやすくなります。
この公報の閲覧が他社技術の調査の基本となります。
ただし、上記の通り、出願から1年6ヵ月経過しないものは閲覧できないので、他にも方法を考えなければなりません。
特許権の侵害訴訟で報道されるケースを分析すると、原告被告の間で同種の製品について激しい開発競争を行っており、出願時期や登録時期、製造販売の開始時期が重複している場合が多いのです。
(3) 無効理由の調査
① 無効資料の調査
第1回の「警告されたらおわりなのか」で述べたように、特許庁では出願に係る発明の属する技術分野について、先行技術の調査を行いますが、周辺技術はある程度の範囲までしか調査しないので、そこに拒絶理由があっても発見できず、特許査定をする場合があります。
無効理由調査は、審査官の見落としの可能性も考慮し、特許庁の調査済みの分野についても調査しますが、そこで見落としがないのを確認した上で、特許庁が調査していない周辺技術分野を調査することに力点をおきます。
特許庁が調査済みの分野については、特許公報を検索すると、そこに調査済みの技術分野のコード(IPCコード)が付されているので、それによってわかります。
そこで、その分野を中心とした周辺技術で特許庁が調査しなかった分野まで、調査範囲を広げていくのです。
調査対象は、主に特許庁に蓄積されている出願情報であり、これは、自分のPCで特許電子図書館にアクセスして調査することもできるし、特許庁まで行き、調査用端末を使って調査することもできます。
そこで発見できない場合、国立国会図書館などで過去の文献を閲覧するなどして調査する場合もあります。
② まず和解を図る
うまく無効理由を発見できた場合はどうすればよいでしょうか。
すぐに無効審判を請求すべきでしょうか。
確かに無効審判の無効審決が確定すれば、特許権は消滅し、原則として誰でも事由にその特許を無効にされた発明に係る製品を、製造販売することができます。
「誰でも」という点に気をつけなければなりません。
手間と時間と経費をかけて無効審判を請求し、無効審決を勝ち取ると、その果実はみんなに分け与えられることになります。
しかし、自分が現在の特許権者にライセンスを受けて製造販売している形を取って、無効理由を審判で公開しないでおけば、他のライバルの参入を防ぐことができるかもしれません。
他のライバルには無効理由が発見できないかもしれないからです。
現在の特許権者に対し、無効審判を請求すれば無効となることを納得させることができれば、権利者は秘密を守ってもらうほうが自分に利益があると判断し、安価ないしは無料でライセンス契約を結んでくれる可能性があります。
他のライバルに対しては特許権という抑止力を維持することができ、しかも権利行使されないという利点があるのです。
③ 侵害訴訟で特許法104条の3の主張
上記の和解が成立せず、侵害訴訟を提起された場合、侵害訴訟で無効理由があることを主張することにより、権利行使を免れる判決を得ることができると第1回「5.売られたケンカは買わなきゃならない」で述べました。
それを特許法に明文で規定したのが、特許法第104条の3です。
民事訴訟の判決は、原則として訴訟当事者にしか効力が及ばないので、この理由で特許権者に勝訴しても、この段階ではあくまで当事者間では権利行使されないという決定に過ぎず、特許権は存続しています。
従って、他のライバルがその特許に係る発明を利用した製品を製造販売すれば、特許権の形式的な侵害であることには変わりありません。
ただし判決文により、無効理由は世に知られるので、他のライバルに対する抑止力は限定的です。
④ 無効審判の請求
侵害訴訟では、権利の有効性、侵害事実の有無、差止範囲、損害賠償についての故意・過失の有無、損害額など、争う事項が多岐にわたるのが普通です。
上記③の主張が認められれば、もちろん勝訴することができますが、その主張以外にも、原告の多岐にわたる主張に対し対応する必要があります。
そこで、特許の有効性のみを争う無効審判を請求し無効審決が確定すれば、特許権は遡及消滅し、侵害訴訟の根拠が消滅するので、そちらに集中する方法もあります。
この場合には、裁判所が必要と認めれば、審決が確定するまで訴訟手続を中止されます。
そして、特許権の消滅により、当該特許に係る発明は、自由に実施することができるようになります。
ただし上記②で述べたように、権利が消滅しているので、他のライバルの誰でも製造販売等が可能となってしまいます。
* 知的財産権や訴訟についてお馴染みでない向きには、ちょっと分かりにくいお話だったかもしれません。
この件について、また、他の知的財産権などについてご質問、ご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。